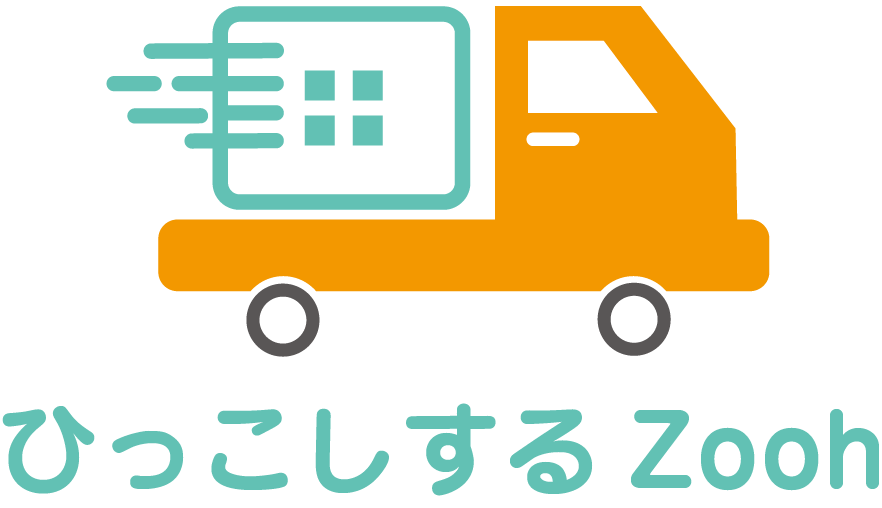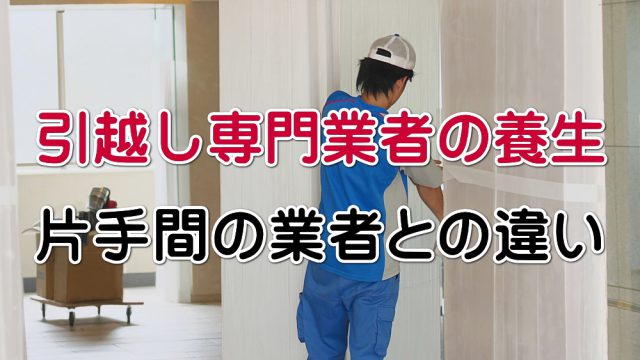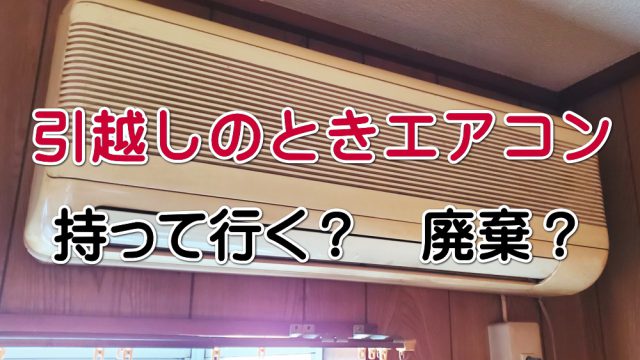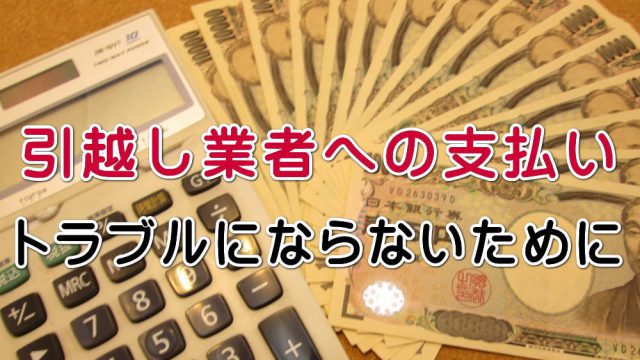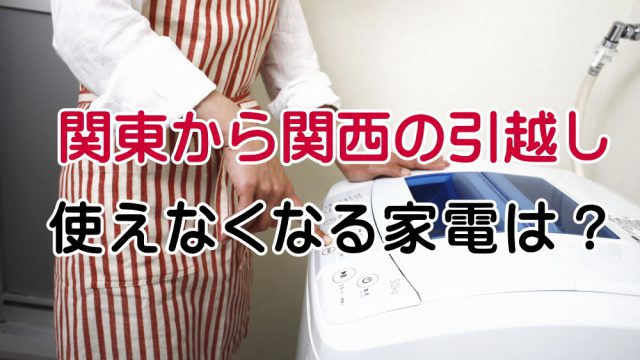本記事はプロモーションが含まれております
ペットと一緒に暮らしている人にとっては、ペットをどうやって引越し先まで連れて行くかという点がもっとも気になるところです。
家族の一員であるペットは、安易に家具のように荷物扱いをするわけにはいきません。
ここでは、犬やネコ、熱帯魚などと引越しをする際に知っておいた方がいいと思われる豆知識を紹介してみたいと思います。
ペットをどうやって引越し先まで連れていくか
ペットを引越し先まで連れて行く方法として、一番無難なのは家族と一緒の乗り物で移動することです。
しかし、乗り物によってはペットを乗せることが出来ない場合もあります。
さまざまなケースについて、ペットの移動方法を考えてみましょう。
犬やネコは飼い主と一緒に移動するのが一番
犬やネコを引越し先まで連れて行くには、飼い主と一緒に同じ乗り物で移動するのが一番です。
マイカーを使って移動する
マイカーでの移動であれば、家族と一緒にペットを乗せて移動をすれば問題ありません。
長距離の移動だと、車に乗り慣れていない犬やネコは多少ストレスを感じるかも知れませんが、家族と一緒であれば問題なく目的地まで行けるはずです。
問題になるのは、家族が公共の交通機関やタクシーを利用する場合です。
タクシーを利用する
タクシーの場合ですと、あるサイトのアンケート調査によると、94%のタクシー会社が可能だと回答しています。
最終的には運転手の判断だと思いますが、よほどの大型犬などでなければ乗車拒否される可能性は低いと思われます。
バスの場合は事前に必ず確認を
バスの場合ですが、市営バスなどであればケージに入れた状態であれば乗車可能なところも多いようですが、大型犬などは乗車できません。
高速バスの場合ですと、たとえケージなどに入れてもペットの持ち込み禁止となっているところが多いようです。
飼い主が高速バスを使って移動をする場合は、事前にバス会社に確認をしておくといいでしょう。
電車はケージに入れればOK
電車の場合ですが、JR東関東であれば犬やネコの全身が隠れケージに入れれば、持ち込みが可能なようです。
また、ペットカートのバッグ部分なども制限内の大きさであれば、分解したうえで持ち込みが可能になっています。
持ち込み可能のサイズとしては、一辺の最大長さが70cmで、縦横高さの合計が90cm以内となっています。
重量は、最大で10kgまでとなっています。
いずれにしましても、実際に持ち込む前に改札口で必ず係員に確認してもらうことが大切です。
ちなみに、乗車料金は280円となっています。
飛行機で移動する場合に注意すべき犬種
 飛行機の場合は、機内にペットを持ち込むことは出来せんので、基本的に家族と一緒に移動するというのは不可能です。
飛行機の場合は、機内にペットを持ち込むことは出来せんので、基本的に家族と一緒に移動するというのは不可能です。
ペットクレートを利用することになりますが、JALの場合は1区画あたり5,000円程度かかるようです。
ただし、フレンチブルドッグやブルドッグは、機内でうまく呼吸をすることが出来ずに死んでしまうことが多いので、預かってもらうことが出来ません。
これらの犬種を飼われている方は、別の移動手段を考えるようにしましょう。
また、規定のサイズを超えたペットの場合貨物扱いとなることがあり、その場合は移動中に水やえさなどを与えることが出来ないために、ペットの健康状態には十分気を付ける必要があります。
船であれば、家族と一緒の客室で移動も可能
最後に船での移動の場合ですが、こちらはペットと一緒に客室に泊まることが可能であるケースが多いようです。
また、船によっては客室とは別にペットルームが用意されていることもあります。
その場合の料金は、1000円から5000円程度と、それほど高くはありません。
犬小屋や熱帯魚の水槽などを運ぶ
犬小屋や熱帯魚の水槽などを引越し先まで運ぶとなると、サイズにもよりますが結構かさばりますし、場合によっては追加料金が発生する場合もあります。
犬小屋を引越し先まで持っていく場合
 外で犬を飼われている場合ですと、犬小屋があると思います。
外で犬を飼われている場合ですと、犬小屋があると思います。
犬にとっては住み慣れたお家ですので、なんとか引越し先までもっていってあげたいと思うものです。
しかし、大型犬用の小屋ともなるとかなりのサイズになりますし、そのまま持っていくとなるとかなりのスペースを占領してしまうことになり、業者によっては追加料金が発生することもあります。
うまく解体が出来るタイプの犬小屋であればいいのですが、そうでない場合は事前に引越し業者に相談してみるといいでしょう。
また、あえて引越し先まで持っていかずに、新しい犬小屋をむこうで購入するというのも1つの選択肢でしょう。
熱帯魚の水槽を運ぶ際の注意事項
 熱帯魚の水槽というのは、たっぷりと水が入っていますので、かなりの重量になります。
熱帯魚の水槽というのは、たっぷりと水が入っていますので、かなりの重量になります。
大型の水槽になるとその重さは200kgほどになりますから、まさにピアノ並みの重さと言えるでしょう。
基本的に、そのままの状態で運ぶのは不可能ですので、水を抜いて運ぶことになります。
水を抜く前に、熱帯魚は事前にビニール袋などに移動し、酸欠防止のために袋の中に酸素を充填します。
また、水槽の水もすべて抜いてしまわずに、ある程度残しておくことが大切です。
水を残すことにより濾過バクテリアが水槽内に残りますし、引越し先で100%新しい水にすると水質が合わずに魚が弱ってしまうこともあるからです。
さらに引越しの時期が冬場ですと、保温についてもしっかりと考えなければなりません。
ビニール袋をしっかり保温して、水温が下がるのを防止しなければなりません。
クーラーボックスなどがあれば、その中に袋ごと熱帯魚を入れて運ぶようにするといいでしょう。
また、長時間の移動となる場合には、ビニール袋内の水質が糞で悪化するのを防ぐために、引越しの前日からエサはやらないようにしましょう。
熱帯魚は2~3日エサをあげなくてもまったく問題ありません。
引越し業者の中には、これらの水槽の引越し作業をオプションとして引き受けてくれるところもありますので、自分でやるのが困難な場合には事前に確認しておくといいでしょう。
引越し先でやっておくべきこと
ペットと一緒に無事引越しを終えたあとにも、やるべきことがいくつかあります。
あとになってトラブルにならないように、忘れずに実行するようにしましょう。
ご近所さんへのあいさつ
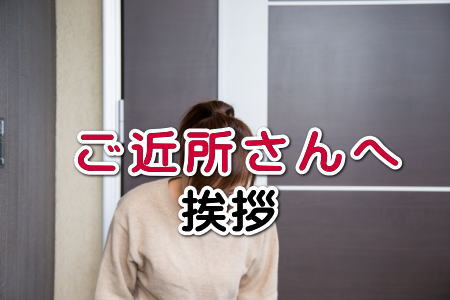 引越しをした際には、ご近所さんに挨拶をすることは常識ですが、このときにペットを飼っていることを正直に伝えるようにしましょう。
引越しをした際には、ご近所さんに挨拶をすることは常識ですが、このときにペットを飼っていることを正直に伝えるようにしましょう。
ペットを飼っていない人にとっては、近所から聞こえてくる犬の鳴き声などは、結構ストレスになるものです。
事前にペットを飼っていることを伝えているかいないかで、相手の方に与えるストレスの度合いも違ってきます。
「ペットを飼っているので、申し訳ありませんが鳴き声がうるさいことがあるかも知れません」
その一言だけでも、十分にトラブル防止効果があります。
関連記事:引越しの際に知っておくべきマナー
熱帯魚であっても一応は伝えておく
飼っているのが犬やネコであれば、一応近所の方にその旨伝えておくことはマナーですが、熱帯魚の場合はどうなのでしょうか?
熱帯魚は犬やネコのように鳴かないので、別に内緒にしておいてもいいような気がします。
しかし、実際に水替えの際に水をこぼしてしまって階下の人に迷惑をかけたという事例や、水槽にエアーを送っているポンプの音が夜中にうるさいと、トラブルになった事例も実際にあるようです。