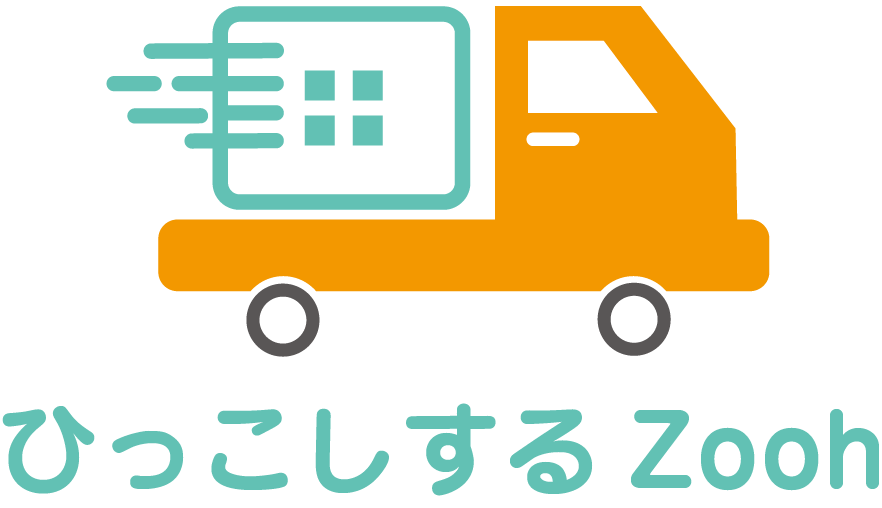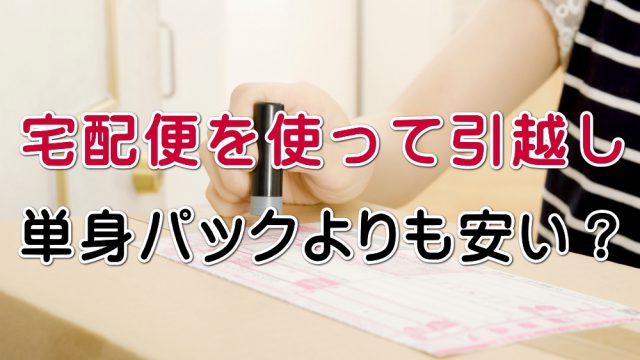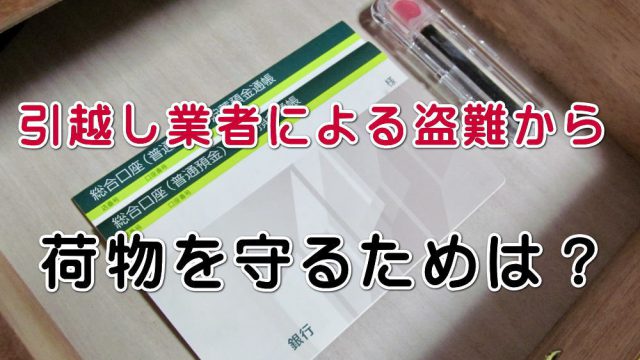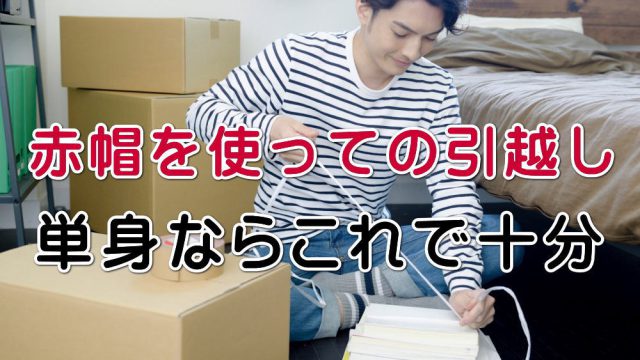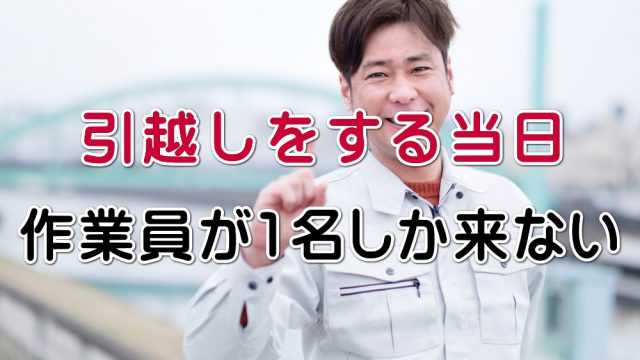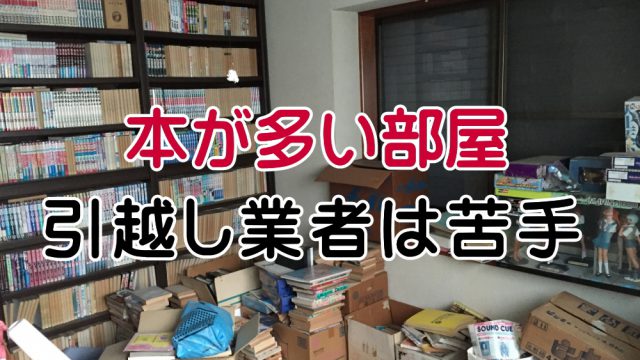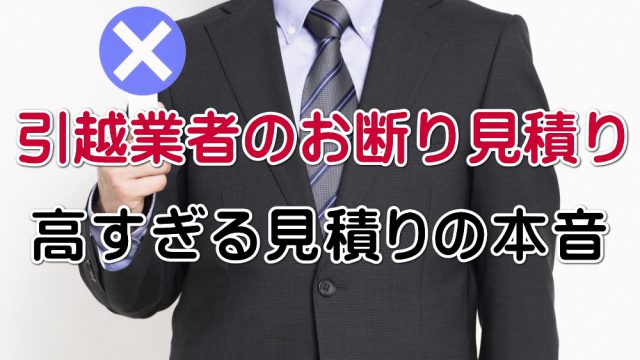本記事にはプロモーションが含まれます
引っ越しのためにいままで住んでいた部屋を出て行くときには、元通りの状態にする義務があるといわれています。
いわゆる原状回復と呼ばれているものです。
しかし、原状回復に関する知識がまったくないために、大家のいいなりになってしまっている人も少なくありません。
本来であれば大家が負担すべき分まで入居者の負担にさせられて、敷金がまったくもどってこないどころか、不足する分を追加で負担させられるというケースもあるのです。
ここでは、賃貸物件を出て行くときに、借主にどこまでの原状回復義務があるのかについて解説をしてみたいと思います
本来であれば敷金が返ってくるのはあたりまえ
敷金というのは、賃貸物件を契約するときに大家に預けておく、いわば担保金ということになります。
家賃を滞納したときの立て替えや、入居者の過失によって建物に損傷が生じたときの修繕費用にあてるというのが、敷金の目的になります。
入居中にそういったことがなければ、退去するときに全額戻ってこなければ、本来はおかしいわけです。
かつては「礼金は戻ってこないけど敷金は戻ってくる」というのが常識でした。
しかし、最近ではどれだけ部屋をきれいに使っても、敷金が1円も戻ってこないというケースも普通にあるのです。
なぜなら、本来であれば敷金で負担すべきではない費用まで、敷金によって賄われてしまっているケースが少なくないからです。
関連記事:引越しで敷金を返してもらうコツ
古い畳の交換費用まで入居者負担にした悪質不動産業者
賃貸物件の退去時に、部屋のすべての壁紙交換代、ハウスクリーニング代、畳の交換代、エアコンの清掃代として、不動産業者から14万円の請求をされた人がいます。
家賃は5万円で、敷金として2ヵ月分を預けていましたが、それだけでは足りずに追加で4万円を支払うように要求されたのです。
壁紙の交換といっても、特にひどい状態であったわけではなく、わずかなスリ傷があった程度です。
畳にしても、古くて傷んでいるから交換するとの理由でしたが、入居時にはすでにだいぶ古くなっていた畳ですから、今回退去する人には原状回復の義務はありません。
そういった理不尽な請求であっても、原状回復の知識がない人は、悪徳不動産業者や大家の言いなりになって、払う必要のないお金まで支払わされてしまうことになるわけです。
原状回復は具体的にどこまでが義務なのでしょうか?
 原状回復義務の本来の定義というのは、「部屋を退去する際に、借主は入居時の状態にできるだけ近づけなくてはいけない」というものです。
原状回復義務の本来の定義というのは、「部屋を退去する際に、借主は入居時の状態にできるだけ近づけなくてはいけない」というものです。
ここで注意をしなければいけないのは、あくまでも「入居時の状態にできるだけ近づけなくてはならない」という点で、決して「入居時の状態に完全に戻す」ということではないのです。
以前は、この原状回復義務の定義があいまいであったために、先ほどあげた事例のように、悪徳不動産業者や悪徳大家の不当な見積もりに泣かされる人も多かったのです。
ところが、1998年に建設省(現在の国土交通省)が、『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』を制定しました。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン-国土交通省より
その結果、「原状回復とうのは、借主が借りた当時の状態に完全に戻すということではい」ということが明文化されることになりました。
つまり、通常の使用や経年劣化による損耗などの修繕費は、敷金ではなく家賃に含まれるものであるということがはっきりとしたのです。
負担すべきなのはハウスクリーニング代金のみ
『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』に従って先ほど紹介した事例を見てみますと、もともと古かった畳の交換や、壁紙の交換、エアコンの清掃代金については、原状回復義務がないということになります。
壁紙にわずかなスリ傷があったという点が微妙ですが、かりにそのスリ傷を自分がつけてしまったとしても、部屋のすべての壁紙を張り変える必要はないわけです。
壁紙の交換費用を負担しなければならなかったとしても、スリ傷のある部分の壁紙だけを交換すれば十分で、費用的には数千円で済んでしまいます。
ハウスクリーニングも、要するに普通に住んでいた部屋を掃除するだけですから、本来であれば貸主側が負担すべきものです。
通常の使用によって多少部屋が汚れてしまうのは、借主には責任がないからです。
しかし、東京都の賃貸物件の9割近くが、特約によりハウスクリーニングは入居者負担と決められているようです。
こういった特約が有効なのかどうかは裁判でも判断が分かれるようですが、あきらかに不当な金額を請求された場合以外は、入居者が負担するのが一般的になっているようです。
つまり、先ほど紹介した事例の場合ですと、入居者が負担すべきなのは、ハウスクリーニング代金と壁紙1枚の張り替え費用のみで、トータルで3万円程度が妥当だと思われます。
追加で4万円も支払うなんてとんでもない話で、2ヵ月分納めていた敷金のうち3万円を差し引いた7万円が返ってこなければ本来はおかしいのです。
貸主と借主のどちらが負担すべきかの判断基準
『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』にもとづいて解釈をすれば、通常の使用や経年劣化による損耗などの修繕費は敷金ではなく家賃に含まれる、ということになります。
しかし、通常使用や経年劣化による損耗なのか、借主による過失による損傷なのかは、具体的にどのように判断をすればいいのでしょうか?
ここでは、大まかな目安を紹介してみたいと思います。
壁紙は画びょうの穴と釘の穴で判断がことなります
 壁紙の場合ですが、基本的に経年による色焼けは貸主の負担で補修をしなければなりません。
壁紙の場合ですが、基本的に経年による色焼けは貸主の負担で補修をしなければなりません。
壁紙というのは、借主にまったく過失がなくても、直射日光や電気製品の熱などによって色焼けを起こしてしまうものだからです。
ただし、注意をしなければならないのは、電気製品の推奨設置距離です。
この距離を守らないことで壁紙に色焼けを起こしてしまった場合には、借主の負担となってしまうことがあります。
また、画びょうによる穴なども、借主には責任はありません。
なぜなら、普通に生活をしていたら、カレンダーなどを壁紙に画びょうで止めるのは当然の行為だからです。
ただし、釘の穴やネジの穴などのやや大きめの穴は、借主の負担となってしまうことがあるので、壁掛けの時計などを取り付ける際には注意が必要です。
また、壁紙の交換ですべての責任が借主にあるとされるのが、タバコのヤニです。
部屋でタバコを吸う習慣のある人は、退去時に壁紙の交換費用を請求されることを覚悟しておかなくてはなりません。
家具の搬入などで床につけた大きなキズの修繕費用は借主負担
床の場合は、日常生活を普通に送るうえにおいて生じる程度のキズや汚れは、基本的に借主には責任がないとされています。
しかし、物を落とすなどの過失によって生じてしまった大きなキズや著しい汚れは、借主が修繕費用を負担することになります。
引っ越しのとき、家具を搬入搬出する際に床などを傷つけてしまうというケースもありますが、こういった場合も当然ながら借主の負担となります。
損傷の程度によって、補修かフローリングを交換するかを判断することになります。
ただし、引っ越しのときに業者がキズをつけたということに気がつけば、保険で修繕費用を負担してくれますので、しっかりとチェックをすることが大切です。
畳を汚してしまったり損傷してしまったりしたときに覚えておきたいのは、借主負担で交換しなければならないのは、あくまでも汚れや損傷のある畳1枚だけでいいということです。
大家によっては、1枚だけ新しい畳だとかっこうが悪いので、全部交換してほしいと主張するかもしれませんが、応じる必要はまったくありません。